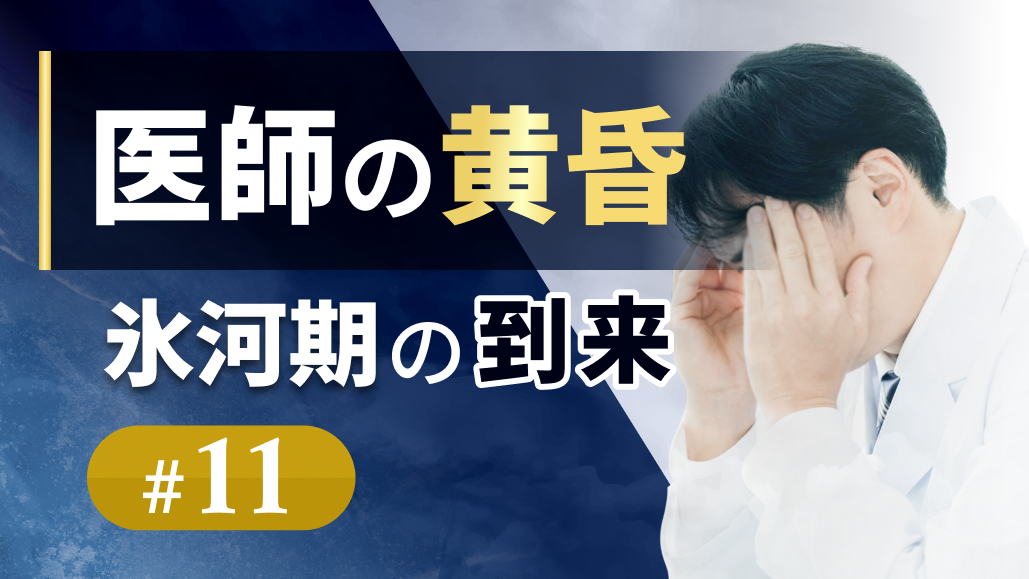ポスト
【特別企画】診療中に感じた 「苛立ち」 への対処法~腫瘍内科医3人の実体験~
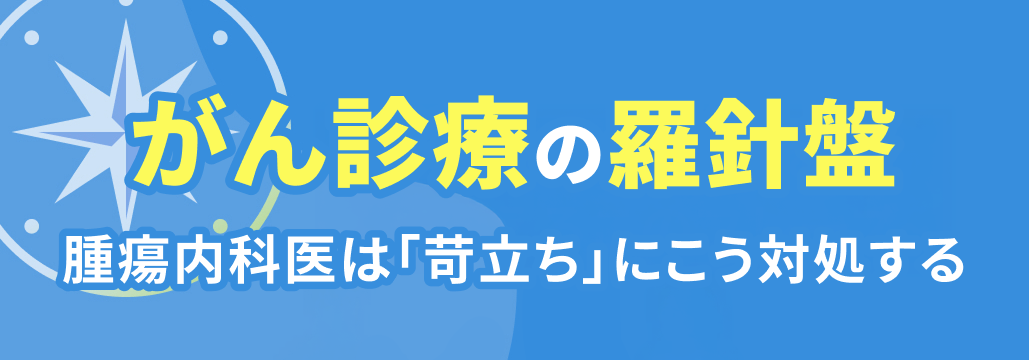
7人の腫瘍内科医による共同企画 「がん診療の羅針盤」、 第25回となる今回は特別企画として、 これまでに反響が大きかった「『患者さんに苛立った』ときの具体的な対処法」をテーマに、 3人の先生方が診療の場で実際に 「苛立ち」 や 「困難感」 を感じたエピソードと、 気持ちを切り替えるための具体的な対処法をご紹介します。
「がん診療の羅針盤」 第22回 : 山口雄先生
Case1 : 三浦裕司先生の場合
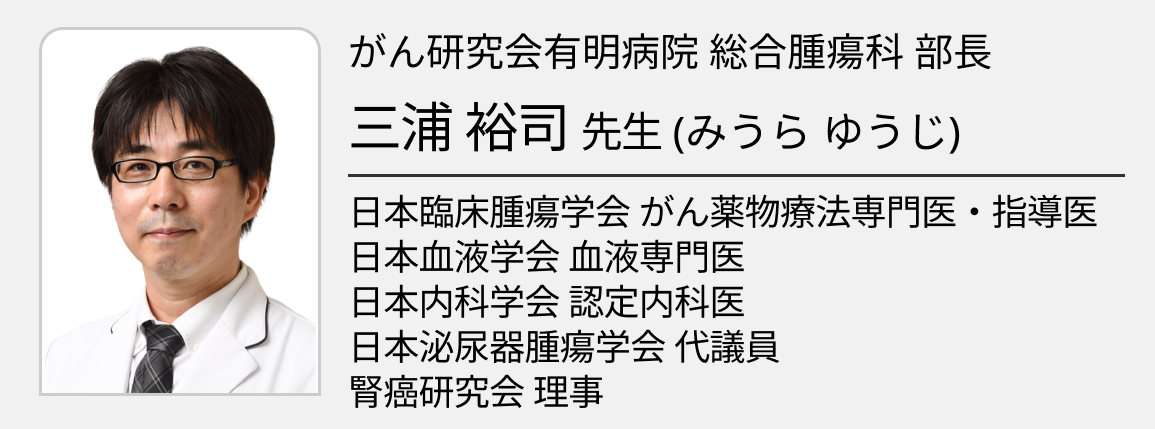
私が 「苛立ち・困難感」 を感じる瞬間
まず、 自分自身の体調が優れない時は苛立ちを感じやすくなります。
体調を整えていても、 刻々と外来の待ち時間が長くなっていくとこちらも焦ってしまいます。 そのような中、 診察室に入室された患者さんから開口一番に、 待ち時間が長いことへの嫌味を言われたり、 怒りを向けられたりするとどうしても苛立ちを覚えてしまいます。
具体的な対処法 : 先手を打って患者の心にアプローチ
体調管理に関しては、 外来前日は遅くまで仕事をせずに、 睡眠時間をしっかり確保して診療に臨みましょう。 低血糖も天敵ですので、 朝食をしっかり摂る、 ポケットに飴ちゃんを忍ばせておくといった心掛けも重要です。
外来診療に関しては、 私はとにかく 「先手を打つこと」 にしています。 患者さんから何か言われる前、 たとえば診察室に入室された瞬間に、
「お待たせして本当にすみません」
「ごめんなさいね、 今日は予想外に説明が必要な患者さんが多くなってしまいまして」
など、 こちらから先に謝罪すると、 それ以上怒りや不満をぶつけてくる患者さんはほとんどいません。 不思議と、 謝ることで自分自身も穏やかな気持ちになる気がします。 「今日は一日中謝っていたな」 と思う日も珍しくありません (笑)
上手く対処できなかった時の原因・反省点
昔は苛立ちを覚えると、 「なぜ待ち時間が長くなったのか」 を説明 (言い訳) していました。 しかし、 その説明がさらに待ち時間を長くさせてしまう上に、 システム面の不備に関する不満を畳み掛けてくる患者さんも多く、 余計に苛立ってしまうこともありました。
Case2 : 近藤千紘先生の場合
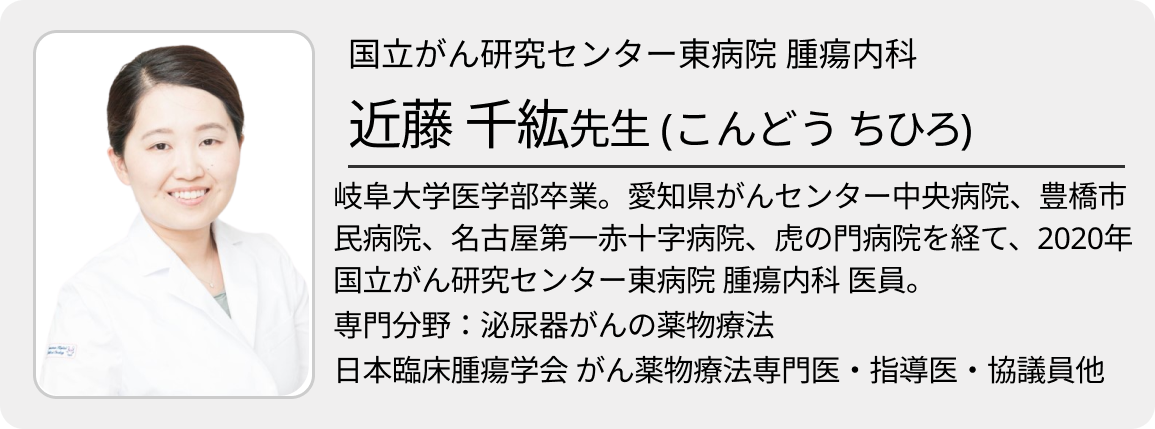
私が 「苛立ち・困難感」 を感じる瞬間
「苛立ちを覚える時」 は、 患者さん側の要因というよりは、 医療者側のコンディションに起因することが多いように思います。 医療者側に時間の余裕がないときや、 ほかに優先して対応すべき事項があるとき、 普段ならば苛立ちもしないことまで気になってしまうのかもしれません。
病に苦しみ、 日常生活に困っている状況を相談したいという患者さんの思いは、 常に存在すると感じています。 例えば抗がん薬の治療開始直後は吐き気や食欲不振、 倦怠感、 筋関節痛、 発熱などの副作用が次々と起こり、 内服の血管新生阻害薬などは口内炎や食欲不振、 下痢、 手足症候群などの特徴的な副作用が起こります。 そのような時期の患者さんはたくさんの不安を抱えているため、 ついつい話が長くなりがちです。
診察で対応できる時間は患者さん1人当たり5~10分程度が平均的ではないかと思います。 限られた時間の中で、 副作用を乗り越えるための効果的な方法を常に考えながら診療にあたっています。
具体的な対処法 : 治療開始前から患者に情報提供を行う
治療開始直後の患者さんには、 副作用の内容や対応についてできる限り事前に情報提供することで不安を払拭し、 副作用の出現に備えます。
具体的には
- 吐き気止め、 解熱剤、 抗菌薬の使い方を事前にお伝えし、 処方しておく
- 日々の症状を日記帳などに記載してもらうようお願いする
などの準備をしておくことで、 短い診療時間でも大きな達成感を得られるように思います。 副作用だけでなく、 日常の困りごとも多々生じるため、 看護師や薬剤師、 栄養士、 理学療法士、 ソーシャルワーカーなどに適宜相談できる体制を整えると、 より患者さんの満足感は上がると感じます。
また、 患者さんによって適切な診療頻度は異なるため、 薬の副作用パターンとご本人の不安感を意識して、 個々の状況に応じて診療スケジュールを決めています。
このほか、 外来診療に追われている際に、 看護師さんや事務員さんが 「先生、 大変ですね」 と労ってくれるとホッとして穏やかな気持ちになれます。 大変なのはお互いさまの環境ですので、 日頃からほかのスタッフへの気遣いも重要であることに気づかされます。
上手く対処できなかった時の原因・反省点
院内スタッフとの関係がまだ十分に構築できていない状況では、 医師自身が患者さんの日常生活の不安や生活環境の確認もしていかなければなりません。 1人の患者さんにかかる時間はおのずと増え、 30分程度必要になってしまうこともありました。 そうすると、 後の患者さんの診療開始時間が遅れてしまい、 結果的にせわしない外来診療になってしまいがちです。
また、 医師自身にアドレナリンが出すぎているときは、 些細なことで苛立ちを感じやすくなります。 そのため、 眠気覚ましとしてのコーヒーの飲みすぎには注意しています。
Case3 : 髙橋萌々子先生の場合
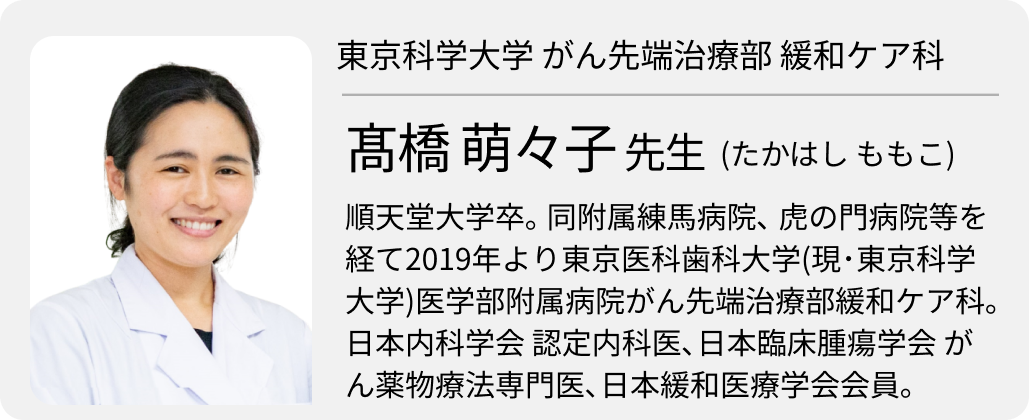
私が 「苛立ち・困難感」 を感じる瞬間
緩和ケア病棟や緩和ケアチームでの診療では、 患者さんがベッドに臥床されたままお話をされることが多くあります。 その際、 患者さんと目線を合わせるためにベッドサイドでしゃがむと高確率で足がしびれ、 患者さんの話に集中できなくなるのが密かな悩みです。
また、 医療用麻薬の導入を検討する時に、 患者さんが医療用麻薬に対する誤解 (依存や副作用への過度な心配など) をお持ちのケースでは、 不安を聴取し丁寧に解きほぐすことで解決する場合もあれば、 やはり受け入れが難しい場合もあります。 そのような時に困難感を感じることもあります。
具体的な対処法 : 無理な体勢は取らずに傾聴の姿勢を示す
最近は、 無理にベッドサイドでしゃがまず患者さんの足元に立つことで目線の高さを何となく合わせる、 あるいはベッドサイドに椅子があれば遠慮なくお借りしています。 椅子に座ったからといって必ずしも話が長くなる訳ではなく、 「話をきちんと聞きます」 という姿勢が示されることで患者さんの満足感が高まるようにも思います。
また、 医療用麻薬への導入に困難感を感じた場合には、 患者さんの生活背景 (子育て中、 仕事で運転が必須など) が絡んでいたり、 「自分はまだ麻薬を使う病状ではない」 といった病状の否認が隠されていたりする場合もあります。 この場合は多職種でのアプローチが有効であると感じます。
上手く対処できなかった時の原因・反省点
患者さんのつらさに寄り添いたい思いから、 自分の足のことは二の次にしてしゃがんで話を聞いてしまい、 しびれの限界が来て立ち上がることで、 話を早く切り上げたいような印象を与えてしまうこともあります。
また医療用麻薬の導入については、 医療者側の 「最善」 に当てはめようとすると患者さんが頑なになってしまいます。 必要な情報を提供しながら、 患者さん自身のタイミングを忍耐強く待つ姿勢も大事であると感じます。
山口雄先生からのコメント
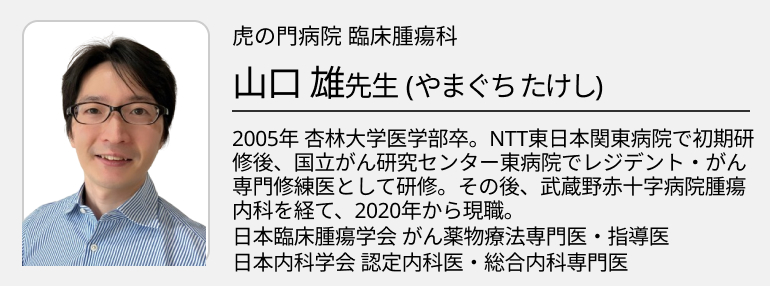
自身の感情から目を背けず、 工夫し続ける姿勢が重要
3人の先生方の経験談を通じて印象的だったのは、 「患者さんに苛立ちを覚える原因は、 患者さん自身よりも医師のコンディションや診療環境に起因することが多い」 という共通した視点でした。 その上で、 「先手を打って謝る」 「副作用説明で先回りする」 「椅子を借りて目線を合わせる」 といった工夫が、 苛立ちを和らげる具体的な方法として紹介されており、 大変参考になる内容でした。
何より大切なのは、 「苛立ち」 という自分自身の感情から目を背けず、 改善のための工夫を考え続ける姿勢だと思います。 その積み重ねが、 より穏やかに患者さんと向き合える診療につながっていくのではないでしょうか。
関連コンテンツ
虎の門病院臨床腫瘍科 山口雄先生
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。