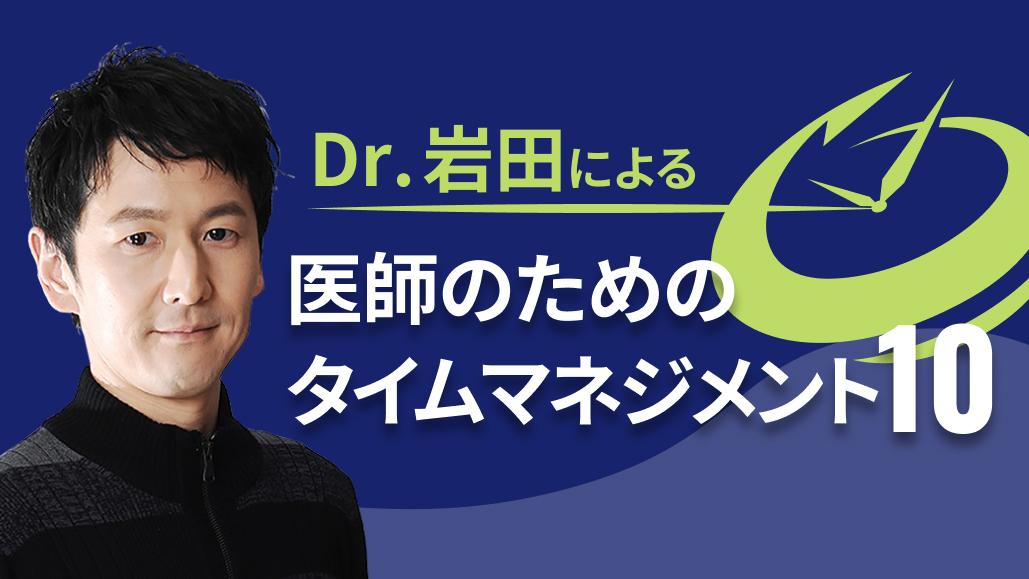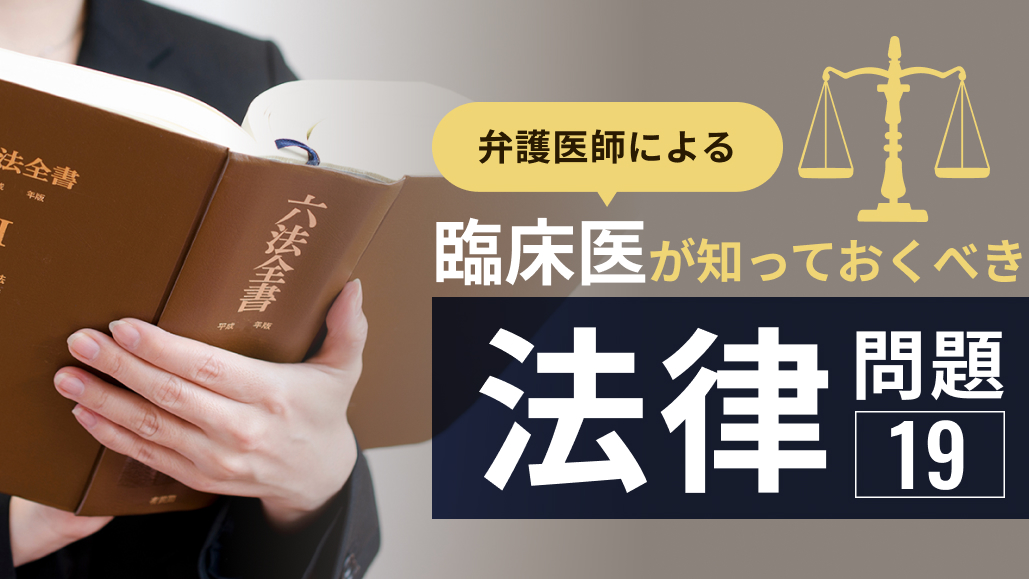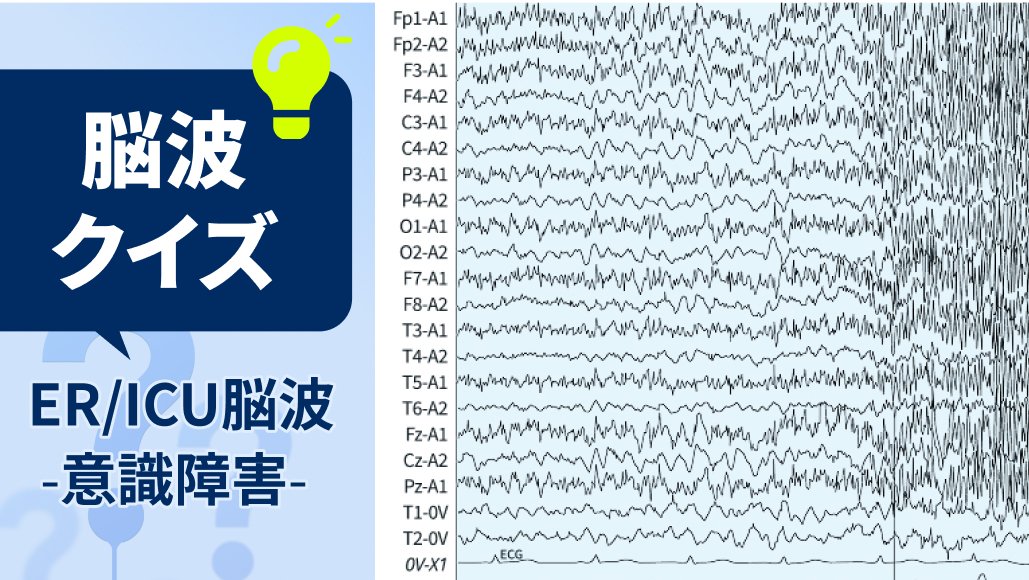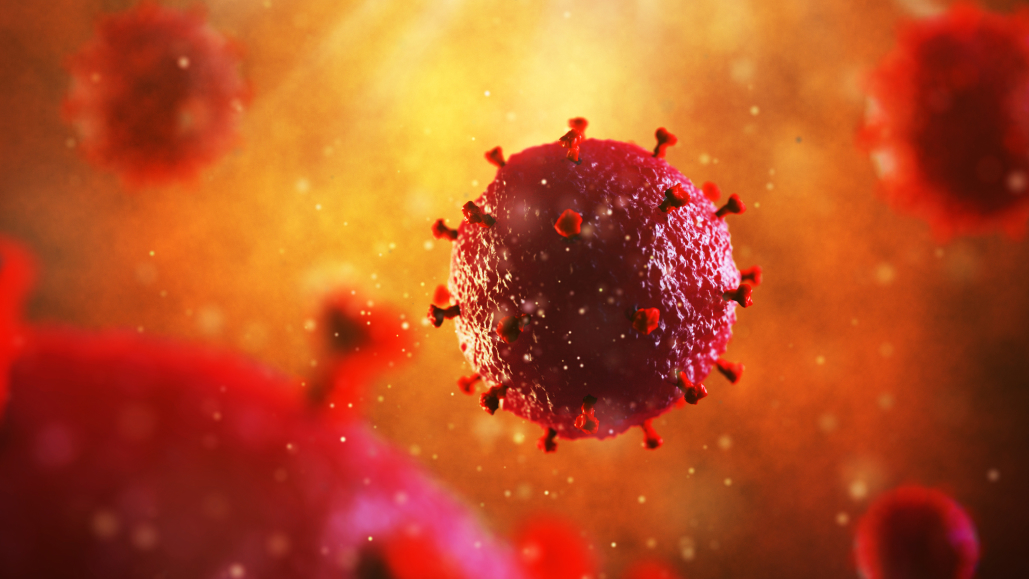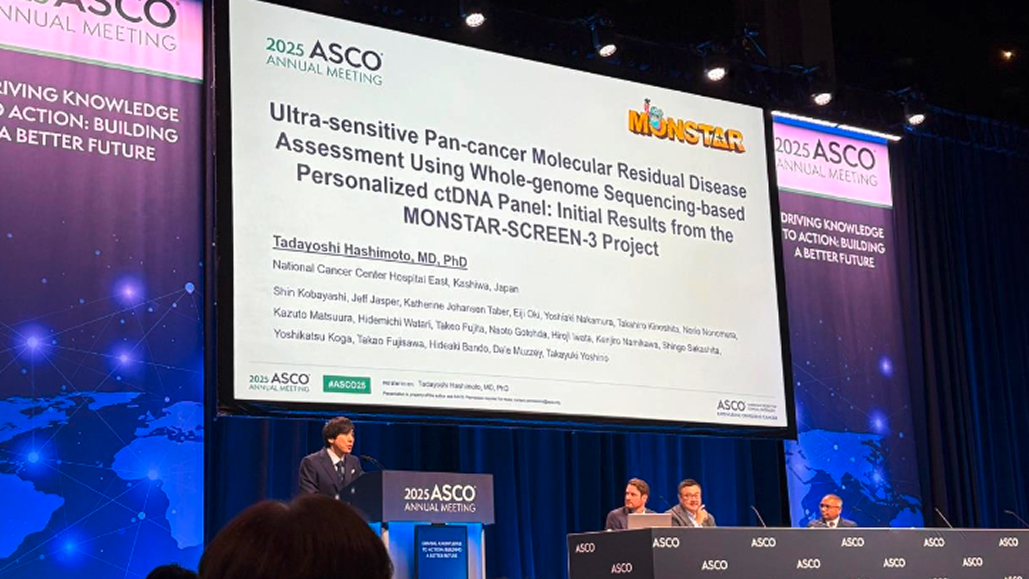ポスト
【NEJM】大腸癌、 術後療法後の運動介入でDFS改善 : 第Ⅲ相CHALLENGE
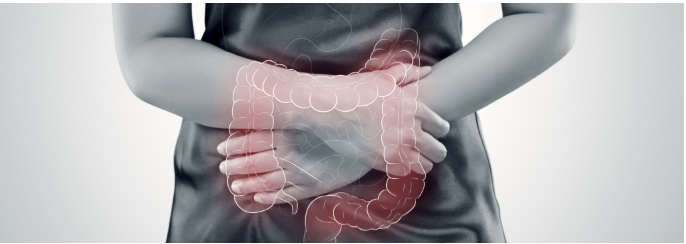
Courneyaらは、 大腸癌の術後補助化学療法を完了した患者を対象に、 運動介入が予後に及ぼす影響を第Ⅲ相無作為化比較試験CHALLENGEで検討した。 その結果、 構造化した運動プログラムにより無病生存期間が有意に延長した。 本研究はNEJM誌に発表された。
📘原著論文
👨⚕️HOKUTO監修医コメント
本研究では、 サンプルサイズ設定時に予測された無病生存期間 (DFS) の値と実際の観察値がほぼ一致しており、 無作為化比較試験における適切なサンプルサイズ設計の重要性を再認識させる結果となりました。
関連コンテンツ
Dig Dis Sci. 2025 Apr;70(4):1511-1520.
Lancet . 2025 Apr 12;405(10486):1231-1239.
目的
大腸癌における運動介入の無病生存期間向上への効果をRCTで検証
運動ががんの転帰を改善する可能性は、 前臨床および観察研究により示唆されてきたが、 これまでにレベル1のエビデンスは存在しなかった。 運動介入が大腸癌の無病生存期間向上に寄与するかどうかを明らかにするため、 本試験が実施された。
研究デザイン
対象は術後補助化学療法を完遂した患者
同試験の対象は、 切除術後に補助化学療法を完遂した患者であった。 患者は、 構造化された3年間の運動プログラムを受ける群 (運動群) と健康教育資料の配布のみの群 (健康教育群) に割り付けられた。 主要評価項目は無病生存期間 (DFS) であった。
結果
DFSは運動群において有意に向上
患者は、 2009~24年にかけて運動群445例、 健康教育群444例に無作為に割り付けられた。
追跡期間の中央値7.9年において、 DFSは運動群において健康教育群よりも有意に向上した (再発・新規原発がん・死亡のHR 0.72、 95%CI 0.55-0.94、 p=0.02)。 5年DFSは、 運動群で80.3%、 健康教育群で73.9%であり、 群間差は6.4%㌽ (95%CI 0.6-12.2%㌽、 p=0.02) であった。
全生存期間 (OS) は、 運動群が健康教育群よりも長く、 死亡のHRは0.63 (95%CI 0.43-0.94)であった。 8年OSは運動群が90.3%、 健康教育群が83.2%であり、 群間差は7.1%㌽ (95%CI 1.8-12.3%㌽) であった。 筋骨格系有害事象は運動群で18.5%、 健康教育群で11.5%に発生し、 運動群で頻繁に発生した。
結論
3年間の運動プログラムでDFSが改善
著者らは、 「大腸癌の術後補助化学療法終了直後に開始した3年間の構造化された運動プログラムによりDFSが改善し、 OS延長と一致する結果を示された」 と報告している。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。