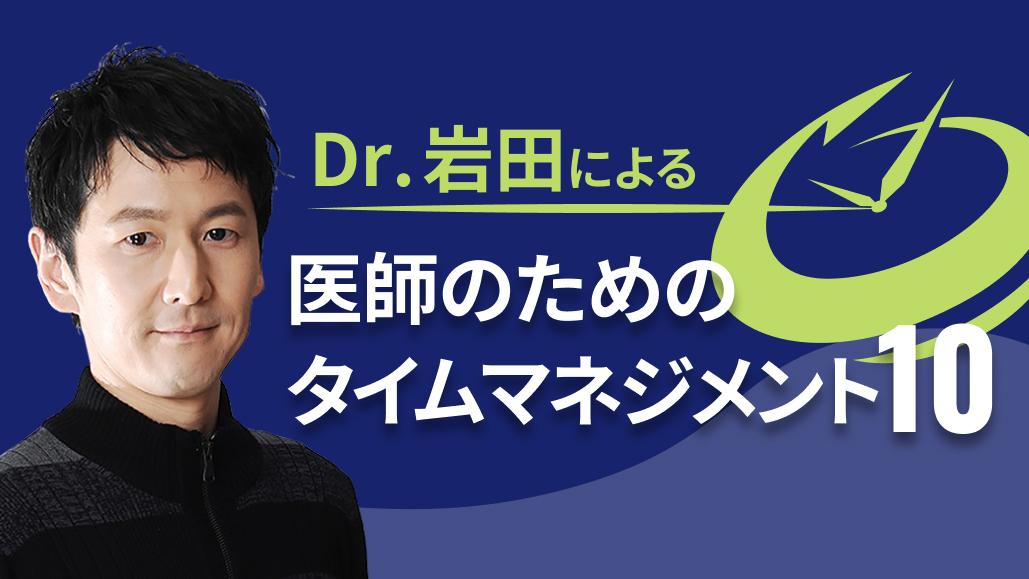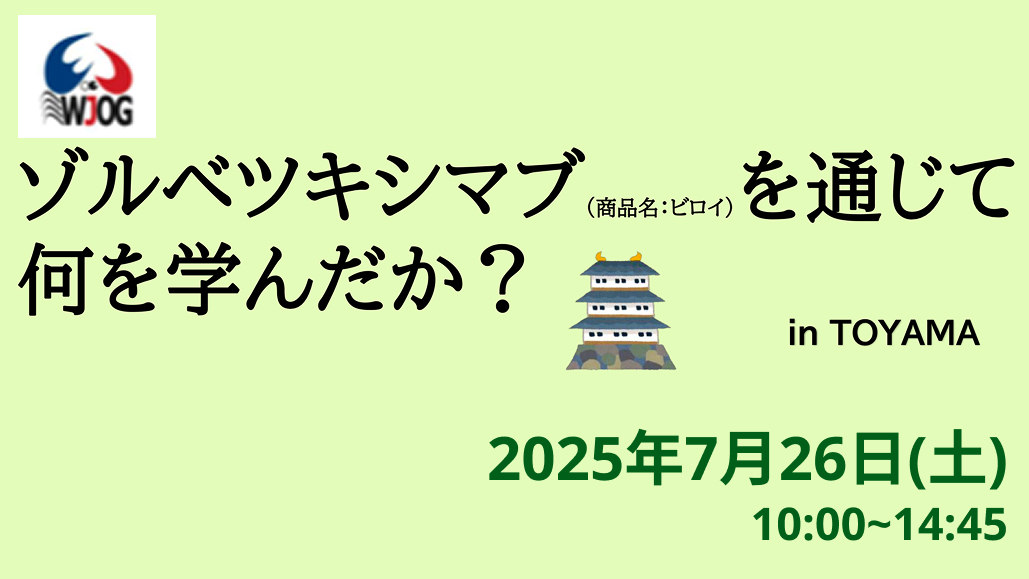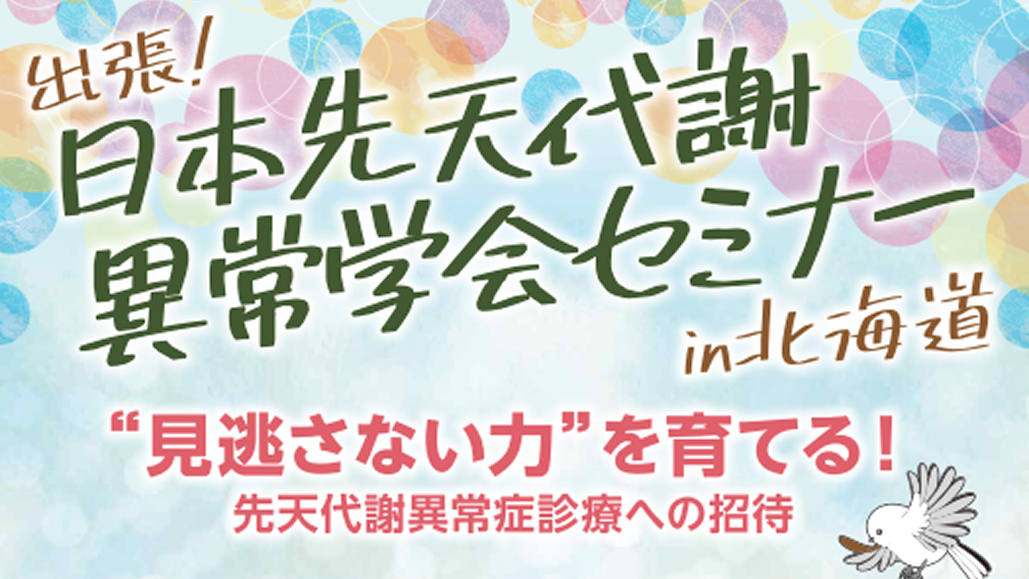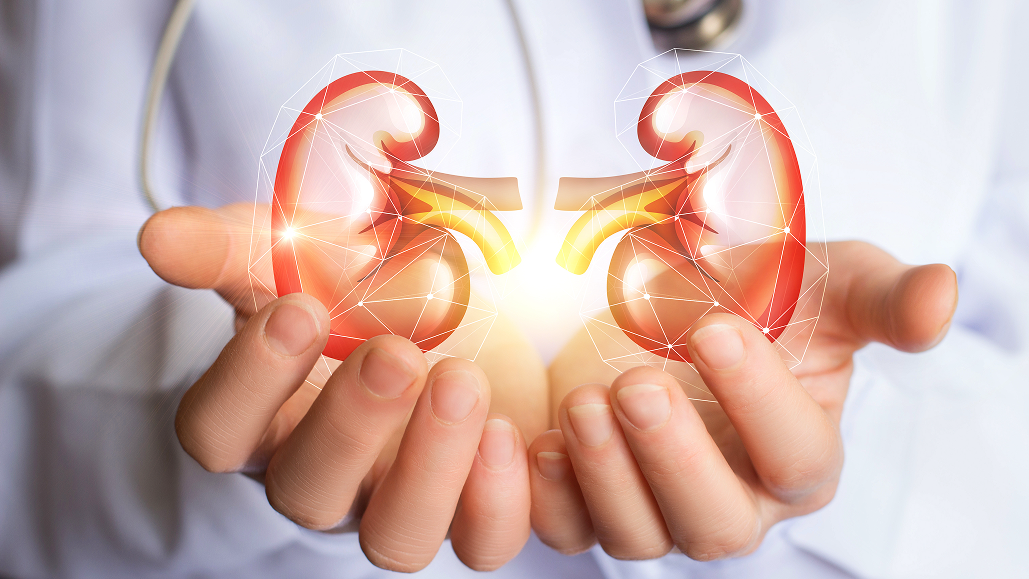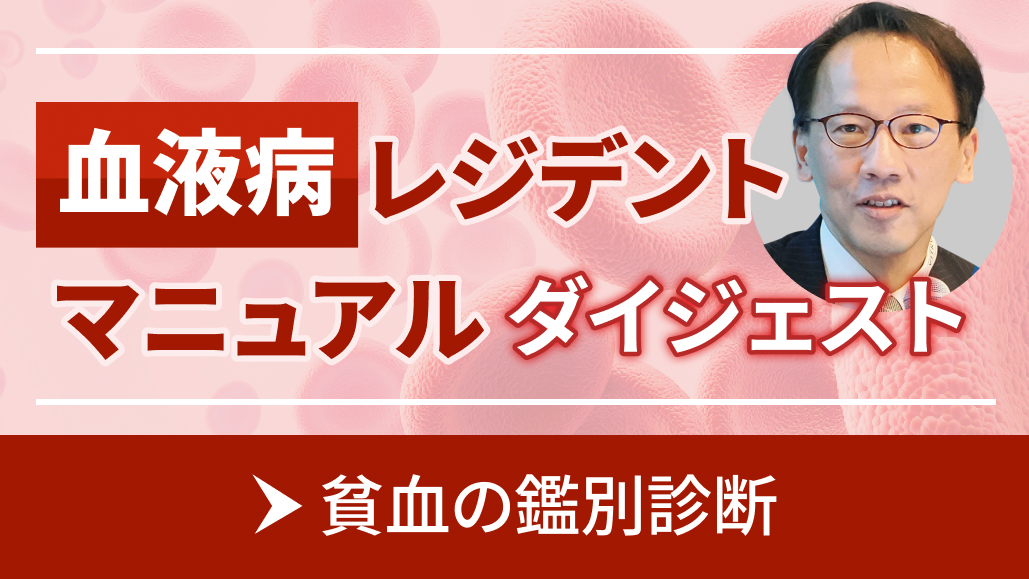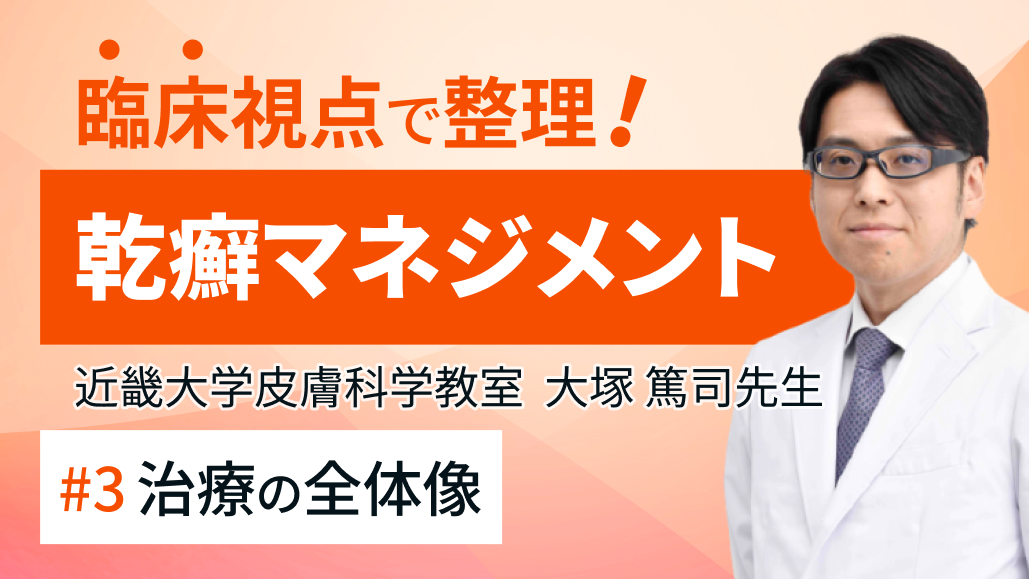ポスト
乾癬治療の全体像 (大塚篤司氏)
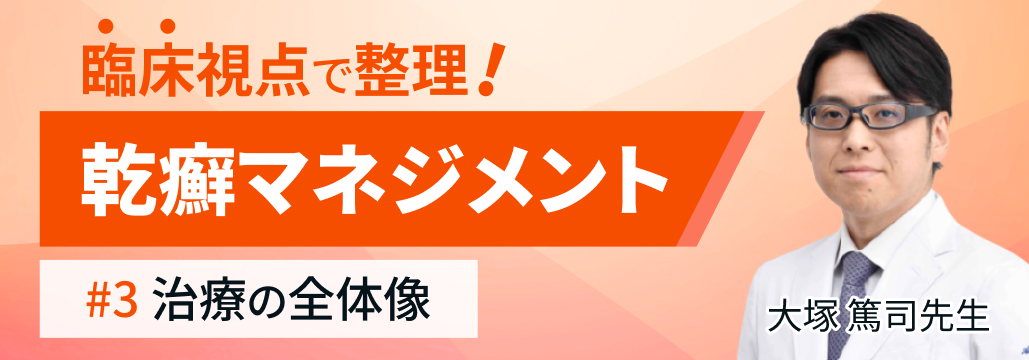
乾癬治療は、 生物学的製剤や新規経口薬の登場により選択肢が多様化しています。 本連載では薬剤ごとの特徴や選択の考え方、 現場での運用のポイントなどを整理します。
はじめに
「どの患者に、 どのタイミングで、 どの治療を選ぶか」 が重要
乾癬治療は、 この10年で劇的な進化を遂げた。 かつては 「一生付き合う病気」 と言われていた乾癬も、 今や 「寛解」 さらには 「見た目にほぼ正常な皮膚」 を目指せる時代となった。
しかし、 選択肢が増えたからこそ、 「どの患者に、 どのタイミングで、 どの治療を選ぶか」 という判断がより重要になっている。 本稿では、 外用療法から最新の生物学的製剤まで、 乾癬治療の全体像を俯瞰し、 実臨床での治療選択の考え方を解説する。
乾癬治療の基本戦略
「治療ピラミッド」 から 「ダイナミックアプローチ」 へ
従来の乾癬治療は、 「治療ピラミッド」 に基づき、 外用療法から始めて段階的にステップアップする方法が主流だった。
しかし現在は、 患者の重症度、 QOL、 ライフスタイル、 治療目標に応じて、 最初から積極的な治療を選択する 「ダイナミックアプローチ」 が推奨されている。
治療選択の軸は、 以下の3つである。
1. 皮疹の重症度
BSA、 PASI、 特殊部位の有無
2. 患者のQOL
DLQI、 仕事・社会生活への影響
3. 全身性炎症の評価
関節症状、 心血管リスク、 メタボリックシンドローム
これらを総合的に評価し、 「今、 この患者に最も適した治療は何か」 を考えることが重要である。
参考記事
治療オプションの全体像
❶外用療法 : すべての治療の基盤
外用療法は軽症例の第1選択であり、 中等症~重症例でも併用される基本治療である。
外用療法の成否は 「いかに続けてもらうか」 にかかっている。 1日2回塗布が負担な場合は1日1回でも継続を優先し、 配合剤の使用も積極的に検討する。
ステロイド外用薬
即効性に優れ、 炎症を速やかに鎮静化する。 強さのランクを使い分け、 長期使用時は週末のみ塗布などの間欠療法を考慮する。
関連ツール
ビタミンD3外用薬
皮膚の過剰増殖を抑制する。 ステロイドより効果発現は遅いが、 長期使用でも副作用が少ない。
配合剤 (ステロイド+ビタミンD3)
両者の利点を併せ持ち、 アドヒアランスも良好。 初期治療や維持療法に有用である。
❷光線療法 : 安全性の高い全身療法
中等症以上で、 外用療法の効果が不十分な場合の選択肢である。
通院頻度がネックとなりやすいが、 寛解導入後は週1回程度の維持療法で良好な状態を保てることも多い。 また、 生物学的製剤導入前のワンクッションとしても有用である。
ナローバンドUVB
最も汎用される。 週2~3回の通院が必要だが、 妊婦や小児にも使用可能。
エキシマライト
局所的な照射が可能である。 頭皮や肘・膝などの難治部位に有効。
PUVA療法
効果は高いが、 光感受性薬剤の内服が必要で、 現在は使用頻度が減少している。
❸内服療法 : 全身性炎症への対応
光線療法が困難、 または効果不十分な場合に検討する。
デュークラバシチニブ (ソーティクツ®)
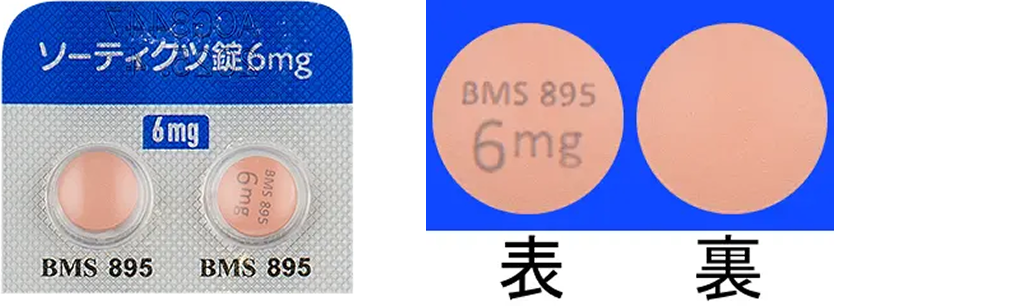
TYK2阻害薬 (JAK阻害薬の一種)。 2022年に承認された、 最新の経口薬である。
生物学的製剤に匹敵する高い有効性を示し、 1日1回の内服で済む利便性が魅力である。
薬剤情報
ソーティクツ錠 6mg
アプレミラスト (オテズラ®)

PDE4阻害薬。 効果は中等度だが、 安全性が高く、 検査も最小限で済む。 初回導入しやすい。 ただし、 下痢などの消化器症状に注意が必要。
薬剤情報
オテズラ錠 10mg / 20mg / 30mg
メトトレキサート
関節症状を伴う場合に特に有効である。 週1回投与でよいが、 定期的な血液検査が必要である。葉酸併用を忘れない。
シクロスポリン
即効性があり重症例に有効だが、 腎機能・血圧のモニタリングが必須である。 長期使用は避ける。
❹生物学的製剤 : 寛解を目指す切り札
中等症~重症例で、 従来治療で効果不十分な場合の切り札。 現在、 複数の製剤が使用可能である。
どの製剤を選ぶかは、 効果の速さ、 投与間隔、 関節症状の有無、 既往歴などを総合的に判断する。 最初の3ヵ月で効果判定を行い、 不十分なら早めにスイッチを検討する。
TNF-α阻害薬 :
インフリキシマブ、 アダリムマブ、 セルトリズマブペゴル
関節症状にも有効。 長期使用実績もある。
IL-17阻害薬 :
セクキヌマブ、 イキセキズマブ、 ブロダルマブ
皮疹への効果が特に高い。 また、 PASI 90以上の達成率が高い。
IL-23阻害薬 :
ウステキヌマブ、 グセルクマブ、 リサンキズマブ、 チルドラキズマブ
投与間隔が長く (8~12週)、 長期寛解維持に優れている。
IL-17A/F阻害薬 : ビメキズマブ
IL-17AとIL-17Fの両方を阻害する。 高い有効性を有する。
❺新規治療薬 : 新たな選択肢
ウパダシチニブ (リンヴォック®)

JAK阻害薬。 乾癬性関節炎に対して2022年に承認された。 関節症状と皮疹の両方に効果を示す。
薬剤情報
リンヴォック錠 7.5mg / 15mg
タピナロフ (ブイタマー®)

アリル炭化水素受容体 (AhR) アゴニスト。 2024年に承認された新しい作用機序の外用薬である。 ステロイドやビタミンD3とは異なる機序で、 1日1回塗布で効果を発揮する。
薬剤情報
ブイタマー クリーム1%
実臨床での治療選択
軽症
BSA<10%、 PASI<10、 DLQI≦5
外用療法 (ステロイド+ビタミンD3配合剤) で治療開始。
中等症
BSA≧10%、 PASI≧10、 DLQI>5のいずれか
外用療法+光線療法 or アプレミラスト。 効果不十分なら生物学的製剤を検討。
重症
BSA≧20%、 PASI≧20、 DLQI>10
早期から、 生物学的製剤の導入を積極的に検討。 QOL改善を最優先に考える。
治療成功のカギ : Treat to Target
現在の乾癬治療は 「Treat to Target (目標達成に向けた治療) 」 が基本理念である。 具体的な目標を設定し、 達成できなければ治療を見直す。
推奨される治療目標
● 3ヵ月後 : PASI 75以上の改善
● 6ヵ月後 : PASI 90以上
理想的にはPASI 100 (完全寛解)
● DLQI 0~1
皮膚症状がQOLに全く影響しない状態
なお、 「このくらいでいいか」 という妥協は禁物である。 現在の治療薬なら、 多くの患者で 「ほぼ正常な皮膚」 を目指せる。 ただし、 患者自身の治療目標も重要で、 必ずしも完全寛解を望まない患者もいることを理解する。
おわりに
乾癬治療は、 もはや 「症状を抑える」 から 「寛解を目指す」 時代へと変わった。 外用療法から生物学的製剤まで、 幅広い選択肢を適切に使い分けることで、 ほぼすべての患者のQOL改善が可能となっている。
重要なのは、 ①早期から積極的な治療介入を行うこと、 ②客観的指標で効果を評価すること、 ③効果不十分なら躊躇なく治療を変更すること、 の3点である。
乾癬は 「治せる病気」 になりつつある。 我々医師には、 その可能性を最大限に引き出し、 患者に希望を与える責務がある。
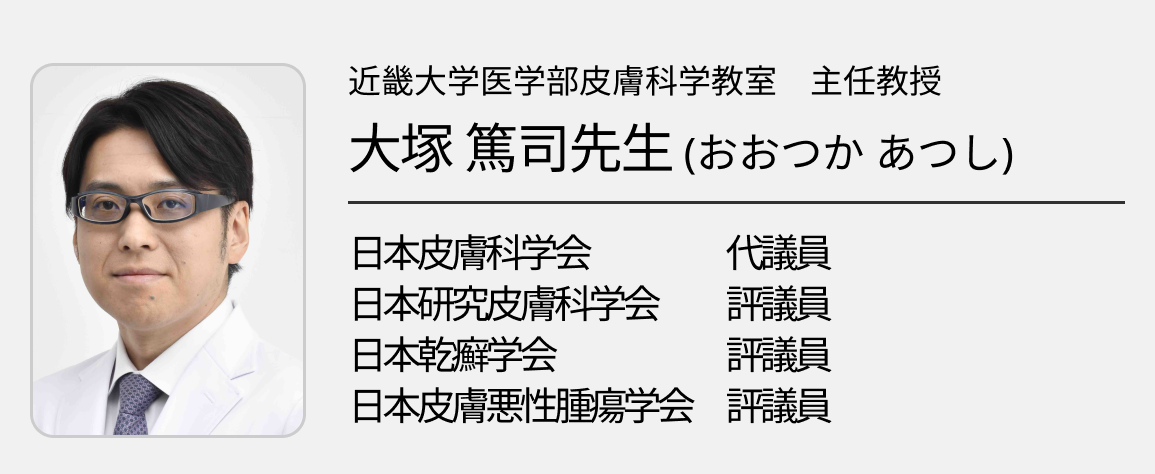
大塚先生執筆の書籍はこちら!
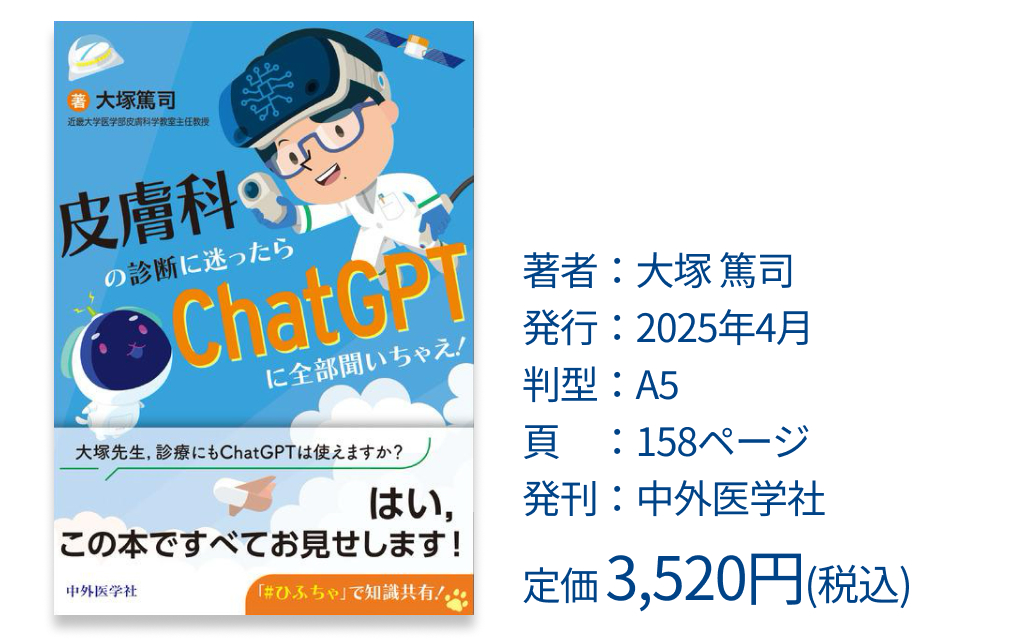
皮膚科の診断に迷ったらChatGPTに全部聞いちゃえ!
紅斑・丘疹・鱗屑など皮疹の"見え方"を言語化し、 ChatGPTで鑑別リストを引き出す手順を症例対話で丁寧に指南。
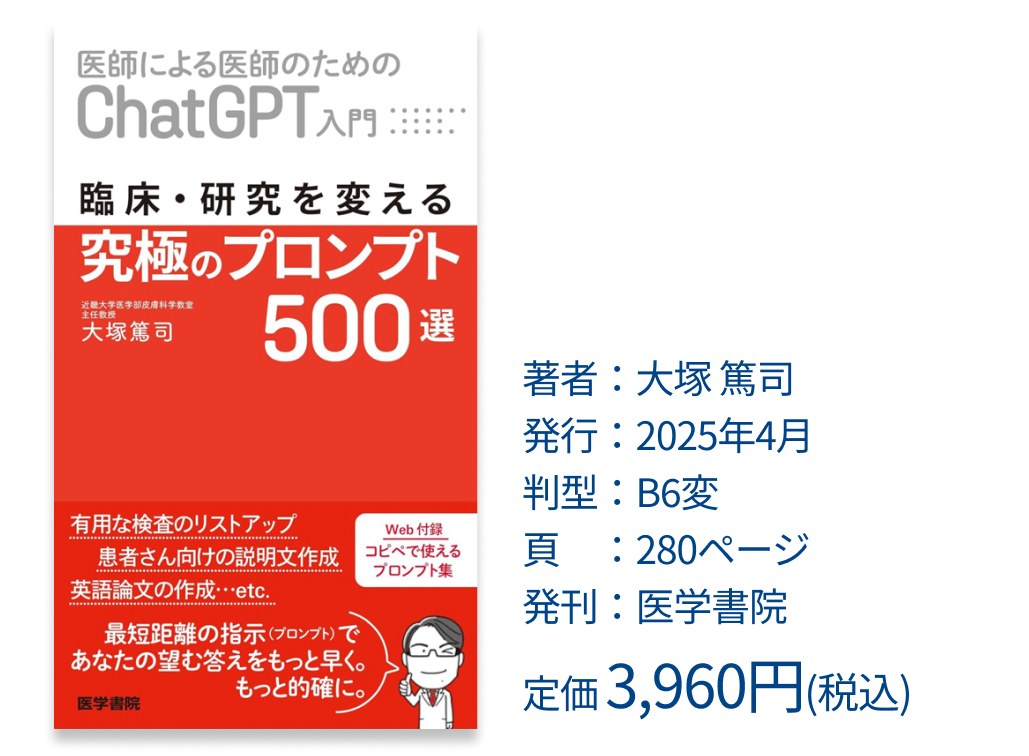
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床・研究を変える究極のプロンプト500選
2025年4月発刊!医療現場でそのまま使えるプロンプトをテーマ別に収載。 日々の診療・教育・研究に役立つ実践的な1冊。
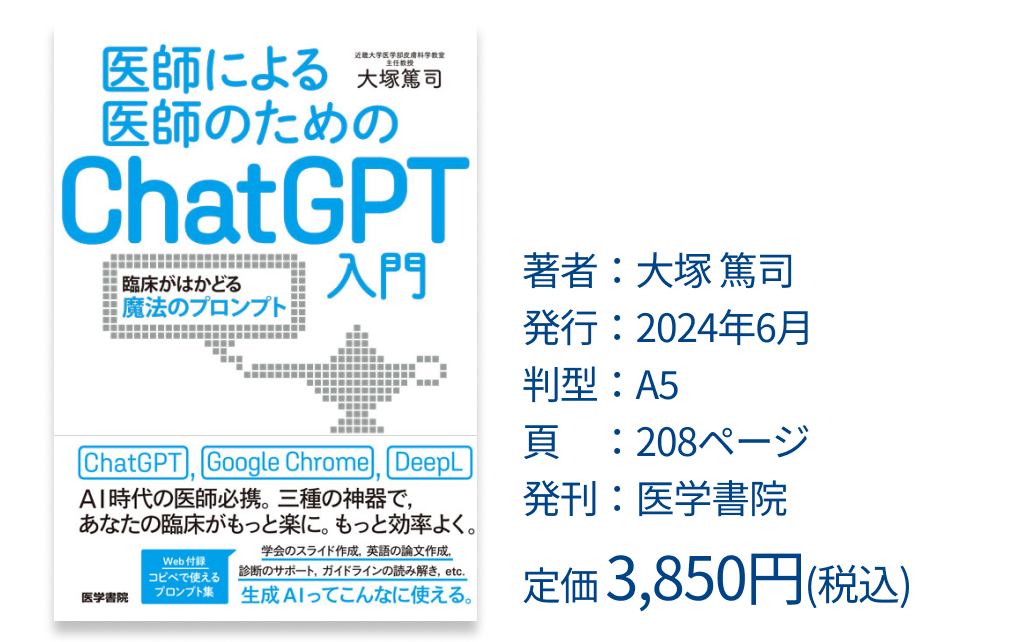
医師による医師のためのChatGPT入門
臨床がはかどる魔法のプロンプト
ChatGPTに苦手意識のある医師に向け、 基本的な使い方から日常業務での活用法までを、 会話形式で丁寧に解説。
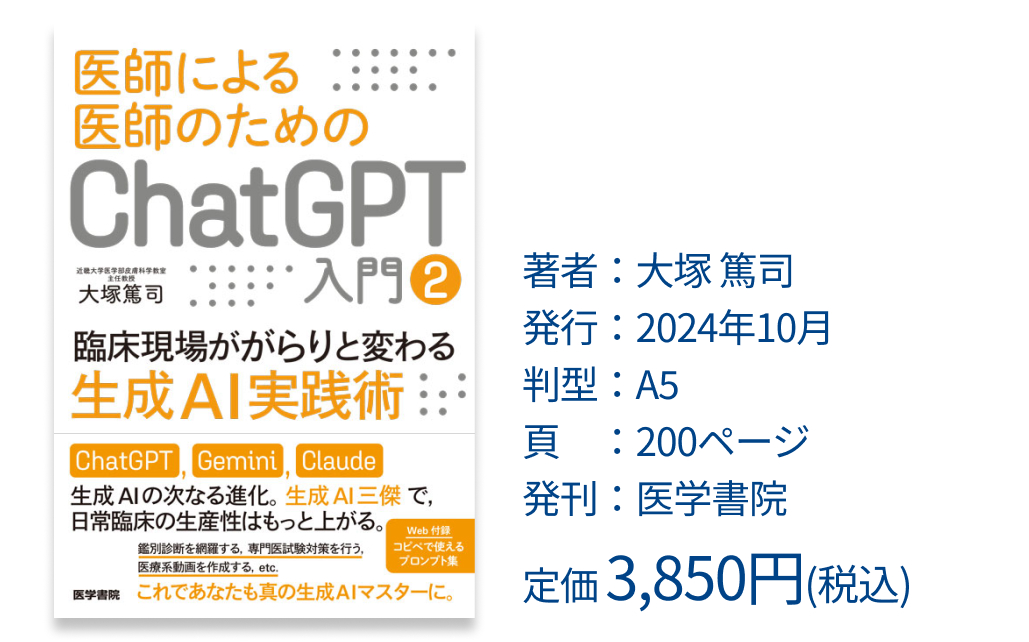
医師による医師のためのChatGPT入門 2
臨床現場ががらりと変わる生成AI実践術
GeminiやClaudeなどの登場で広がる最新の活用法を網羅。 前作に続き、 実例とともに理解が深まる構成。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
人気のポスト
最新のポスト
あなたは医師もしくは医療関係者ですか?
HOKUTOへようこそ。当サイトでは、医師の方を対象に株式会社HOKUTOの臨床支援コンテンツを提供しています。